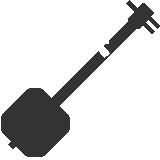
- 島唄四方山話 -
[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
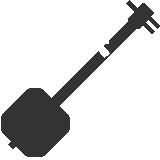
- 島唄四方山話 -
| その3:続々・唄遊びでの唄い方 | 2005.6.26up |
| ■唄遊びでの唄い方⑤ 八月踊りでも同様だが、唄遊びの場でも一節唄い終わらないうちに次の人が被って唄い出す。聴いている側からするとこれが非常に格好良い。 唄遊びは“遊び”であり唄掛けは“会話”だ。決して喉自慢大会ではないので基本的にみんな唄いたくてウズウズしている。だからイントロのつもりで弾いていたら途中から唄い出すなんて当たり前、唄に入っても前の人が終わるか終わらないかの内に次の人が唄い出すのだ。シマのオバァが言ってたが、「口を開けて待ってないといつまで経っても唄えない」そうだ。まるで鳥の雛みたいじゃないか。 なるほど初めのうちは少し間をとっていたが、そのうち盛りあがってくると被り具合が激しくなってくる。これが聴いている側からすると唄が一本の線のように繋がって聞こえ、気持ちいいのだ。 ■唄遊びでの唄い方⑥ 前述したように唄遊びは会話なので、歌詞が問答形式になっているのが理想だ。 例えば下記の通りである。 例①)朝花節 唄者A:唄いじゃさんなやれいじゃさんな (唄者B/囃子) よう言うた物じゃ 例えた物じゃ 唄やしどぅ習りゅんぐゎ 唄いじゃさんなやれいじゃさんな 唄者B:シマ唄ぐゎぬ懐かしゃや (唄者A/囃子) 一や抜からん 今抜からんよ 昔親ふじんきゃぬ シマ唄ぐゎぬ 曲げ美らさ 訳①) A:唄いなさい唄を出しなさい(囃子/巧い事を言った物だ←唄者Aを誉めている) 唄う事が唄を習う事だから 唄を出しなさい B:シマ唄が懐かしい (囃子/あなたが一番。今は誰にも抜かれないよ←唄者Bを誉めている) 昔親や先祖が唄ったシマ唄は曲げ(グイン)が美しいね~ 上記はほんの一例だが、こうして唄で対話をする。 この後、挨拶したり(後述)、恋愛の歌詞を唄ったり、教訓を歌ったり、「そろそろお開きにしようか」というのも唄の上で行う。 唄遊びの会場となる家の主人とお客さんのやりとりといった歌詞もたくさん残されていて、今では定番歌詞となっている。 例②)朝花節 客人:突然いじて憚りながら (家主/囃子) シマや一番 村一番よ ごめんくだされませ 此ぬ家ぬご主人様 家主:参ちゃん人どぅ 真実やらんな (客人/囃子) ヨイサヨイヨイ かためてヨイヤ 石原迫踏み来ち 参ちゃん人どぅ 真実やらんな 訳) A:突然唄い出して畏れ入ります、この家のご主人様。 B:石原や谷を踏み越えていらして来てくれた人こそ真実の人です。 ※現在でも奄美は街灯のない地域が多く、夜出かけたりする時は懐中電灯が必携となる。懐中電灯も無く、道路も未舗装の時代などはそれこそ夜の外出は大変な事だったのだろう。 ※『朝花節』は挨拶、声馴らし、場の清めの唄なのでオープニングに相応しい歌詞がたくさん残されているが、『黒だんど節』にも『俊良主節』にも挨拶の歌詞がある。結局、会話と同じと言う事は自分の言いたい事(=唄いたい歌詞)を唄えば良い訳で、前の人唄った歌詞から極端に話題が変わらなければ良いのだろう。会話と同じという事は前者の話題をふくらませる人が上手な人と呼ばれていたに違いない。 唄遊びは“遊び”でなので、余程の事がない限りあまり細かい事は言われないようだ。 |
|